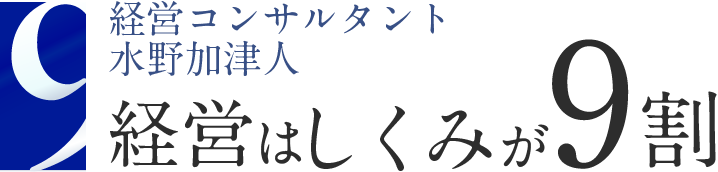Frequently Asked Questions
よくある質問
Frequently Asked Questions
よくある質問
なにから取り組んだらいいかわからなくなっているのですが、それでも大丈夫ですか?
回 答
はい、大丈夫ですよ。
そういう方は非常に多いです。自分のことは自分ではなかなかわからないものですし、ビジネスには正解がないので迷う気持ちもわかります。
この場合は、いくつか自分に問いかけるところからスタートがおすすめです。なぜ、このビジネスを行なっているのか?これからどうしたいか?大切にしていることは何か?理想の人生のイメージがあるか?理想のプライベートのイメージがあるか?などといった経営者個人の想いを明確にすることで、優先順位の整理が進み、やることが明確になって行きます。
多くの経営者が、頑張って色々な打ち手に取り組んでらっしゃいますが、集客・売上優先、部分的な解決法といったものが多く、根本的な解決になっていなくて悩んでいます。それを続けていると結局、課題がアメーバのように広がってしまうのです。解決には、全体をみる思考が必要です。
自問もいいですが、私と一緒にやってみませんか?
「水野さんと一緒にディスカッションをすると自分が考えていなかった視点が見えてくる」という声をよくいただきます。よろしかったら、お手伝いしますので、個別相談をご利用ください。
コンサルティング期間は、どれくらいがおすすめですか?
回 答
会社によってテーマや課題が異なりますので一概には言えませんが、多くの場合は、整理や構築に6ヶ月、実践6ヶ月が目安で、合計1年を最初のステップとして考えていただくことをおすすめしています。多くのクライアント様が1年目で成果を出され、2年目、3年目と継続し、成長・発展のしくみのレベルアップに取り組まれています。
最近ムリが効かなくなって体力的に厳しいので、コンサルティングについていけるか心配です。
回 答
それを解決できるのが、経営のしくみ化です。私は、健康づくりの専門家でもあるので、健康コンサルも同時にご提供できますので、ご安心ください。
コンサルティングの提供方法は?
回 答
オンライン教材が充実していますので、オンラインで効率よく受けていただくことができます。ご希望に応じて、出張もお受けしています。その際は別途、出張費、距離に応じて交通費、宿泊費をいただいています。
コンサルティングは、マンツーマンですか?
回 答
はい、マンツーマンでしっかりサポートさせていただきます。ビジネスの相談はもちろん、個人的な人生の相談などもお受けしています。健康問題の相談をいただき、別途サポートさせていただくことも多々あります。
また、社内にしくみ構築チームをつくりたい場合は、スタッフの同席も可能です。しくみ構築を通じて、スタッフ研修を一緒におこなうこともできます。お気軽にご相談ください。
他のしくみ化コンサルティングとの違いは何ですか?
回 答
私もいままで多数の仕組み化コンテンツを学び、取り入れてきましたが、私の特徴は以下のような感じです。
1.マンツーマンの寄り添い型でおこなう
2.年商1億円超え12年継続のビジネス経営経験と、自走型組織の構築経験がある
3.リアル店舗3つとオンライン両方のしくみ化経験がある
4.集客・売上、組織づくり、財務といった部分コンサルではなく、全体コンサルをおこなう
5.複数のしくみ化メソッドの良い点を提供できる(仕組み経営・協会ビジネス・年商200億グループ企業)
6.軍隊のような型にはめる仕組み化ではなく、経営者とスタッフの個性・特徴を活かすしくみ化を推奨
7.聞く力と質問力の高さに定評があり、クライアント様の発想拡大に喜ばれている
やることが多すぎて、どこから取り組んでいいかわからない状態でも相談していいでしょうか?
回 答
はい、もちろんです。そういった経営者様は少なくありません。
まずは、次の質問を通じて、本当に望んでいる未来を思い描き、優先順位の整理をするところからコンサルティングさせていただきます。
なぜ、このビジネスをおこないたのか
誰を救いたいのか、誰を喜ばせたいのか
どんな未来を描きたいのか
理想の会社
理想の仕事
理想のプライベート
考える際は、月イチ旅の実践がおすすめです。
すぐに時間が取れない場合でも、まずは2時間、ひとりの時間をつくってみてください。
月イチ旅については
私の著書、「経営しくみ化大全」に詳しく書いています。
まだ年商が1,000万円程度なので、しくみ化はもう少し年商が上がってからにした方がいいでしょうか
回 答
実は、こういったご相談はすごく多いのですが、年商レベルはまったく関係ありません。個人事業主でも企業でもうまくいくための構造はまったく同じです。
まずは、ビジネス成功の設計図を知ることがおすすめです。多くの方が、ビジネスが混沌してしまってから相談に来られるのですが、先に設計図を手に入れておこなえば、回避できることも多々あります。
また、課題の解決については、集客・売上、組織づくりといった部分的な打ち手は、一時的には効果的なのですが、多くの場合続かず、体力と気力の限界がきます。なのでおすすめは、全体の構造を意識した最適化へのアプローチです。これも知っているか知らないかの差が大きいので、起業する際に、まずは知っておくと、良いです。
設計図・構造の最適化については
私の著書、「経営しくみ化大全」に詳しく書いています。
採用が難しい・離職が止まらないのですが、そういった内部の相談もできますか?
回 答
はいもちろんです。
採用に関しては、まずは2つのことを考えてみることから始めさせていただいております。
1)採用の際に、報酬や待遇などメリット重視になっていませんか?
多くの採用募集がメリット重視になっています。メリット推しにすると、メリットに価値を感じる人が集まってきます。コロナ禍以降、人の意識の変化が進み、メリットで響かない人が増えてきたと感じます。おすすめは、理念や仕事で得られる価値をしっかり伝えて募集することです。面接の際の質問も同様です。最初が肝心です。良い人を採用して、採用直後の研修、フォロー研修といった一連の流れを理念や価値観をしっかり伝えながら、主体性を促す、自走型人材育成のしくみをつくることがおすすめです。
2)スタッフが働く環境は、スタッフ、お客様双方にとって良いものですか?
多くの日本人は、自分のためより、人のための方がやりがいを感じられます。お客様の喜びの事例などを共有するしくみをつくることがおすすめです。また、スタッフ自身にとっても自分の個性を活かす、同僚から認められる、頼りにされるといった要素も重要で、これらを感じられる環境づくり、人材育成のしくみが必要です。
なぜ、理念が重要なのですか?理念がなくても売上はあがると思いますが。
回 答
はい、売上は理念が曖昧でも上がります。私も経験がありますのでそこは同意見です。
ただし、良いお客様を集めたい、良い人材を採用したい、組織を円滑に運営したい、自走型の組織をつくりたい、会社を長く存続させたいということであれば、理念体系は重要です。
それに賛同する人を集めることで良い環境ができ、ビジネスの成長につながります。
理念体系には、次の5つがあります。
1)ミッション:会社の使命・目的
2)ビジョン:目指す世界を見える化した形で示した目標
3)コアバリュー:活動する上で大切にしたいこと
4)行動指針:バリューを具体的な行動にした例
5)ブランドコミットメント:クライアントにどんな感情を提供したいか?を定義し、明文化したもの
これらは、想いをベースにできています。人は、想いで動きます。メリットは、短期的な行動の原動力につながり、理念体系は、長期的な行動の原動力というとわかりやすいかもしれません。
私は、良い商品や良い人の輪が永続的に広がるといいと思っているので、理念体系を大切にするコンサルティングを行なっています。
現場から抜け出したい。といった相談でも大丈夫ですか?
回 答
はいもちろんです。
あなたが、現場から抜け出せない理由を明確にするところから始めていきましょう。
多くの場合、経営者が現場から離れられないのは、「人に依存した仕組み」が原因です。これを「しくみ依存」に移行することで、現場を手放し、経営者としての本来の役割に専念できるようになります。
売上に不安がある場合は、売上向上のしくみ構築が必要です。人に任せる環境が整っていない場合は、主体性が生まれる環境づくりが鍵です。
また、商品やサービスの質に不安がある場合は人材育成プログラムやシステム活用を検討しましょう。
似たような悩みをお持ちの経営者様にご提供した事例です。
下記の4点を重点的に変えることで、6か月で現場をスタッフに任せる体制ができました。
1.業務の引き継ぎと役割の明確化
2.責任者を明確にする
3.業務の70%を共有化
4.自分たちでマニュアルを作成
まずは、現場から離れられない理由を明確にし、「人依存」から「しくみ依存」への転換を始めてみましょう。それが、あなた自身の自由な時間を生み出し、会社を持続的に成長させる第一歩です。
売上に波があるので、安定させたいのですが、そういう相談はできますか?
回 答
はい、もちろんです。
まずは、波がある理由はを調べるところからコンサルティングさせていただきます。
現在、御社の売り上げに波がある理由は把握されていますか?
たとえば、売上の波をつくる年間スケジュールがない場合は、いつも自転車操業のような状態が続くので、目先の対応になりやすく、経営者もスタッフも疲弊しがちです。
年間スケジュールを立てて、売上の波をつくるしくみへの移行がおすすめです。
会社の決算期をベースに、売上が上がりやすい時期の見極め、そのタイミングでの販売イベント設計を考えます。販売イベントのテーマは、人が集まるを意識して、お客様、見込み客が興味を持って行動するテーマを選ぶと良いでしょう。
人のスキルによる影響の場合は、スタッフの人材育成プログラム構築や外注の活用。オンラインなどのシステム活用なども視野に入れてしくみ化を行うと良いでしょう。
リピート率が低く、いつも新規集客に追われています。リピートを増やしたいという相談はできますか?
回 答
はい、もちろんです。
リピート率向上のためには、リピート設計を見直すことが必要ですので、その設計を一緒に見直していきましょう。
単に新規を追い続けるのではなく、現在のお客様が「再度利用したい」と思える仕組みを構築することで、長期的な安定を図りましょう。
具体的には、以下の4つのステップで進めていきます。
1.商品・サービス提供の質の見直し
2.お客様満足度の確認
3.リピートフローの設計と改善
4.継続不安の解消 → 理想の人生の実現
リピートについて
詳しく知りたい方は
私の著書、「永遠にリピートを生み出す教科書」に詳しく書いています。
これから成長していく道筋が見えないのですが、どうしたらいいですか?
回 答
多くの経営者様の力になってきて思っているのですが、これは、一人では見えないかもしれません。
人は自分のことは、自分ではわかりづらいものです。第三者との対話がおすすめです。その際は、必ずその分野の専門家や同じ立場の方との対話をおこなうと良いでしょう。スタッフや家族などは、立場が違うので、参考になりにくいことが多いです。
私の個別相談をご活用していただいても大丈夫です。
その他の方法としては、市場を見る、時流を見て考えるというもの良い方法です。
3年後の未来は予想しにくくても、10年後の未来は予想しやすいものです。
スタッフが言われたことしかやらず、いつまでも自分が指示しないといけない状態に困ってます。どうしたらいいですか?
回 答
解決案として、経営者に帰属する組織から、理念に帰属する組織への変革。自社に合った自走型の人材育成プログラム構築がおすすめです。
取り組んだ多くのクライアントが成果を出されています。
従業員のお客様対応について、自分(経営者)の思った通りにされないことに悩んでいます。どうしたらいいですか?
回 答
こちらの解決案は、経営者のスキルが再現できる教育のしくみとスタッフへの権限と責任の移行が大切です。
さらに、理念を通じて、なぜ、この商品・サービスを提供しているのか、どんな人を救うのか、喜びを提供できるのかといった価値の再教育の教育のしくみを併用すると効果が高まります。
計画を立てても、立てっぱなしで実現されません。対策を教えてください。
回 答
実現されない理由は、わかりますか?
よくある例としては、経営者の意思決定がコロコロ変わる、同時並行の業務が多い、継続するしくみがない、部分最適の計画になっていて全体への浸透が難しい、計画進捗を確認しサポートする担当者がいない、そもそも計画どおりおこなうのが苦手などがあります。
一人では、原因がわかりにくいかもしれません。コンサルタントやコーチなどの専門家に相談して原因を見極めたうえで、適切な対策がおすすめです。
ルールやしくみを作ったが、継続されないのですが、継続させる方法はありますか?
回 答
継続されない状態には、いろいろな原因が考えられます。
継続するしくみがない、ルールが受け入れにくい内容になっている。しくみが難しい、同時並行の業務が多い、計画進捗を確認しサポートする担当者がいない、原因を見極めたうえで、適切な対策がおすすめです。
継続するしくみのアイデアとしては、事前研修で認知→週間ミーティングで方向性の確認→日報で日々の確認といった流れをつくりつつ、計画進捗を確認しサポートする担当者をつくることがおすすめです。担当者は、同僚同士でチームをつくってお互いをサポートする方法がおこないやすいですが、お互いに不慣れということが起こりますので、専任の担当者をおくのがおすすめです。その際は、実践して結果を出している人を置くことが望ましいです。
幹部やマネージャー層の育成がうまく行きません。いい方法はありますか?
回 答
理念ベースの人材育成プログラムの作成をしながら、教える人を育てるのがおすすめです。人材育成をおこなう場合は、組織の上から育成していくのが望ましいです。人の成長は、以下の4つのステップがありますが、できる幹部でも、教えるスキルが自己流の人が多いです。教えるスキルがバラバラだと、育つ人もバラバラになります。自社の理念に合った、教えられる人を育成することが重要です。また育成の過程を通じて、幹部やマネージャー層のさらなるスキルアップも一緒に行えます。
さらに詳しく知りたい方は、水野の著書「経営しくみ化大全」をご覧ください。